現在確認できる家紋の数
現在、日本で確認できる家紋は6447種類だそうです。
これから家紋を登録しよう、とか、どんなデザインがあるのか知りたい方はこちらから確認してみてください。
何のためにあるの?
一般国民にとっては、その重要性は薄れているかもしれないが、思い出してみよう。
ロゴマークとして認知している高島屋さんや、三井、住友などの旧財閥などのマーク、
これらは、この家を代表するマークで、一目でどこの家の者だか分かるという優れた開発だと思います。
これを考案した人物は、分かりませんが、平安京で牛車に乗る貴族たちがこぞって自分の牛車に掲げて、その煌びやかさを競っていたそうです。

権力者が自分より地位の高いマークと出会ったら、牛車から降りて頭を下げたり、地面にひれ伏していたそうです。
やっぱり、人間ってやることは昔から変わりませんよね(笑)
戦国の武家社会

源氏の家紋「笹竜胆(ささりんどう)」
鎌倉時代から江戸が終わるまでの主役は、みんなが大好きな武家の社会です。
ここでも家紋が大きな役割を果たしていきます。
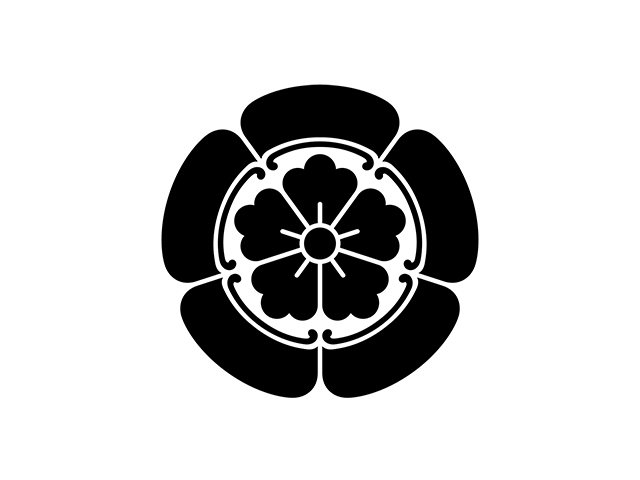
お館様こと織田信長、織田家の家紋「織田木瓜紋」
とはいっても、やはり自分よりも身分が高い人に無礼があっては、即、切腹ですから。
身分の上下でマウントの取り合いの象徴と言えるのかもしれません。
戦場では味方の識別子として重要な役割を果たします。

江戸時代になると、名字が無い身分でも家紋を使うことが認められ、庶民の間で自分の家の家紋を作るブームが訪れて現代に至っているそうです。
現代では?
現代での主な使われ方としては、冠婚葬祭などの式典に着ていく着物につけたり、墓石に刻んだりしています。
おそらくですが、自分の肩書の書かれた名刺がこれに代わった身分の示し方になったのだと思います。
まとめ
家紋とは、代々その家に受け継がれてきた・・・
と、まとめようとしていたのですが、どうもその歴史もそれほど長くなく、名家でもなければ新しく作っても、あまり罰当たりでもないのかな?と思ってしまいました。
家紋のデザインはあまりにも酷いものでなければ、すぐに登録できます。
ココナラなどで、デザイナーに頼んでみたり
自分でデザインして自分だけの家紋を作るのもいいのかもしれません。



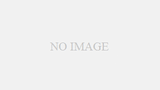
コメント